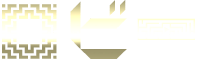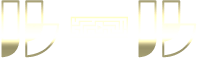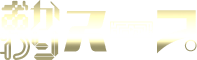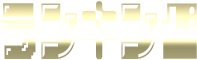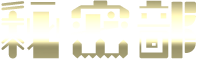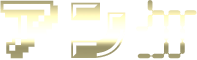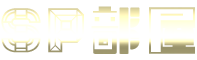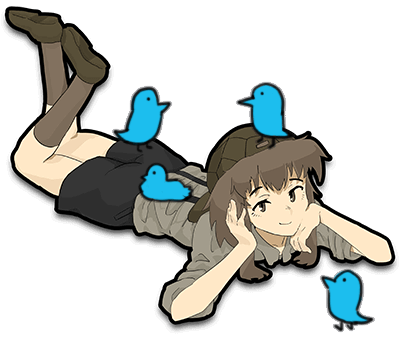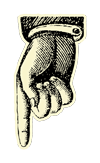「細く長く」「28Good」
良質:12票トリック:2票納得感:14票
蕎麦屋の駐車場が満車なのを見て「今日はお客さんが少ないんだろうねぇ」というカメコの母。
一体なぜ?
某所で出題済みです。色々ご存じの方は色々スルーで。お願いします。

一体なぜ?
某所で出題済みです。色々ご存じの方は色々スルーで。お願いします。
24年01月13日 17:47
【ウミガメのスープ】 [ぴよすけ]
【ウミガメのスープ】 [ぴよすけ]

好奇心を抑えられませんでした
解説を見る
昼下がり。
あの蕎麦屋はいつもこの時間ならとっくにそばが売り切れていてお客が誰もいない状態のはずだから。
らてらての皆様の場合真相解明にどのくらいかかるのかなぁという好奇心を抑えられずに出題してしまいました。
そこそこげんきにしてます。さらば!
λ............トボトボ
あの蕎麦屋はいつもこの時間ならとっくにそばが売り切れていてお客が誰もいない状態のはずだから。
らてらての皆様の場合真相解明にどのくらいかかるのかなぁという好奇心を抑えられずに出題してしまいました。
そこそこげんきにしてます。さらば!
λ............トボトボ
「最愛なるドレスコード」「27Good」
良質:18票トリック:4票物語:5票
スーツを着込んで最愛の女性が待つ豪華客船に乗り込んだ田中。
(今会いに行くからな)
彼女を見つけた後に田中が外したものは何?
理由とともにお答えください。
※理由が合っていなければ不正解とします
ヒント:スーツを着る時に身につけたものです
(今会いに行くからな)
彼女を見つけた後に田中が外したものは何?
理由とともにお答えください。
※理由が合っていなければ不正解とします
ヒント:スーツを着る時に身につけたものです
22年09月01日 23:07
【20の扉】 [ダニー]
【20の扉】 [ダニー]
解説を見る
A.レギュレーター(酸素ボンベ)
豪華客船ロイヤルミルクティー号座礁の報せが航空基地の機動救難隊隊員として働いてる田中の耳に入った。
なんと不運な偶然なのだろう、その船には田中の婚約者である環菜が乗っていたのだ。
船の浸水は予想を上回る速さで進み、田中たち救難隊隊員が現場に着いた時には船はほぼ海に沈んでしまっていた。
ウェットスーツを着込み、レギュレーター(水中で呼吸するための器材)を咥えて沈みゆく船に乗り込む田中。
必死の捜索の結果、田中は環菜を見つけることができた。
最悪のかたちで。
環菜はすでに息絶えていた。
あまりに急な沈没に船内から避難することすらままならなかったのだった。
その変わり果てた姿を見て、田中は絶望した。
彼女は田中の全て。生きるよすがだった。
田中は環菜の体を抱きしめながら、咥えていたレギュレーターを外した。
(今会いに行くからな)
徐々に薄れゆく意識の中、田中は向こうで彼女に会えることを神に祈った。
豪華客船ロイヤルミルクティー号座礁の報せが航空基地の機動救難隊隊員として働いてる田中の耳に入った。
なんと不運な偶然なのだろう、その船には田中の婚約者である環菜が乗っていたのだ。
船の浸水は予想を上回る速さで進み、田中たち救難隊隊員が現場に着いた時には船はほぼ海に沈んでしまっていた。
ウェットスーツを着込み、レギュレーター(水中で呼吸するための器材)を咥えて沈みゆく船に乗り込む田中。
必死の捜索の結果、田中は環菜を見つけることができた。
最悪のかたちで。
環菜はすでに息絶えていた。
あまりに急な沈没に船内から避難することすらままならなかったのだった。
その変わり果てた姿を見て、田中は絶望した。
彼女は田中の全て。生きるよすがだった。
田中は環菜の体を抱きしめながら、咥えていたレギュレーターを外した。
(今会いに行くからな)
徐々に薄れゆく意識の中、田中は向こうで彼女に会えることを神に祈った。
「lim(x→1) 1/x=疲弊」「27Good」
良質:15票トリック:5票納得感:7票
カメコが見た数字が分数だったなら、その値が1に近づけば近づくほど、
整数だったなら、その値が大きくなればなるほど、カメコの疲労は溜まっていく。
これは○○が壊れたからだというが、○○は何?
※○の数と文字数は関係ありません
※同義可
整数だったなら、その値が大きくなればなるほど、カメコの疲労は溜まっていく。
これは○○が壊れたからだというが、○○は何?
※○の数と文字数は関係ありません
※同義可
23年01月23日 23:23
【20の扉】 [ベルン]
【20の扉】 [ベルン]
解説を見る
エレベーター
エレベーターが壊れ、階段で自宅(50階)まで登る羽目になった小学生のカメコ。
階段に書かれた階数が大きくなるほどカメコは疲れていく。
階と階の間の踊り場に書かれた数(例えば二階と三階の間だと3/2など)が1に近づく(最後は50/49になる)ほど高層階となる(画像参照)
※画像はTwitterより拝借しました
エレベーターが壊れ、階段で自宅(50階)まで登る羽目になった小学生のカメコ。
階段に書かれた階数が大きくなるほどカメコは疲れていく。
階と階の間の踊り場に書かれた数(例えば二階と三階の間だと3/2など)が1に近づく(最後は50/49になる)ほど高層階となる(画像参照)
※画像はTwitterより拝借しました
「降り注ぐ日差しがあって だからこそ日陰があって」「27Good」
良質:15票トリック:6票納得感:6票
今日はずっと雨が降りそうな天気だったのでコンビニに向かったカメオ。
しかしすぐに分厚い雲が無くなり、だんだんと晴れてきた。
さてこの時太陽の光が綺麗に○に映っていたため、コンビニからの帰り道、カメオは赤の他人であるカメコを殺した。
○は何?

しかしすぐに分厚い雲が無くなり、だんだんと晴れてきた。
さてこの時太陽の光が綺麗に○に映っていたため、コンビニからの帰り道、カメオは赤の他人であるカメコを殺した。
○は何?
23年04月09日 20:09
【20の扉】 [ベルン]
【20の扉】 [ベルン]

だからこそ日陰「も」あって おかぷ中
解説を見る
月
狼男のカメオ。
分厚い雲が覆っていたのでまぁコンビニくらいなら大丈夫だろうと外出したところ、突然晴れてきた。
そして満月の光がカメオを照らし、狼男となったカメオは隣を歩いていたカメコを殺してしまった。
※満月の光=月に映った太陽の光
狼男のカメオ。
分厚い雲が覆っていたのでまぁコンビニくらいなら大丈夫だろうと外出したところ、突然晴れてきた。
そして満月の光がカメオを照らし、狼男となったカメオは隣を歩いていたカメコを殺してしまった。
※満月の光=月に映った太陽の光
「人と入れ替わることができる口紅(理沙子)」「27Good」
良質:3票トリック:9票物語:10票納得感:5票
およそ残酷な形で恋人に捨てられ、借金で困窮し、また頼れる友達をも失ってしまった理沙子は、絶望の淵で怪しげな路頭商人から口紅をもらった。
曰く、『人と入れ替わることができる口紅』である。使用者が自身の唇に付着させた上で任意の相手とキスをすると、その相手と身体を入れ替えられるというもの。
理沙子は、自分の絶望に満ちた人生を捨てようと思い、それを用いることにした。
ターゲットは、大学の後輩である美里。その容姿と天衣無縫で活発な性格から皆に愛される存在だった。自分のような、陰気で卑屈な日陰者とは大違いだった。
理沙子は計画的に口紅を用いることにした。美里と入れ替わったあとに、美里の友達などに怪しまれてしまっては立つ瀬がない。非現実的とはいえ、仮にもこの口紅の存在や正体が露見することはあってはならない。自分が実は美里ではないと、疑われてはいけない。
入れ替わった後にも周りから怪しまれることがないように、理沙子は美里のことを徹底的に研究した。
彼女の身長、体重、誕生日、血液型、好きなアイドル、親の名前…。誰かに尋ねられそうな事象はひとまず頭に叩き込んだ。
彼女が大学に遅刻しそうな時の表情、友達の欠席を心配する悲しげな表情、仲間を責め立てる表情。彼女の振る舞いも研究した。陰気な自分を押し殺し、いわば美里をトレースするのだ。
理沙子は美里の狼狽する姿を想像した。普段から笑みを絶やさない美里が、自分のような逸れ者の立場を手に入れてしまったことを自覚し、焦りに飽和する姿。想像するだけで、理沙子は似合わない優越感が生まれるようで面白い。
——————
さて、実際に理沙子が口紅を使用した後、理沙子は記憶障害のふりをした。無事成功して入れ替わったというのに、そこで美里のふりをすることは一切しなかったのだ。
では、どうせ記憶障害ということにするのに、理沙子はなぜ美里のことを先のように徹底的に研究したのだろうか?

曰く、『人と入れ替わることができる口紅』である。使用者が自身の唇に付着させた上で任意の相手とキスをすると、その相手と身体を入れ替えられるというもの。
理沙子は、自分の絶望に満ちた人生を捨てようと思い、それを用いることにした。
ターゲットは、大学の後輩である美里。その容姿と天衣無縫で活発な性格から皆に愛される存在だった。自分のような、陰気で卑屈な日陰者とは大違いだった。
理沙子は計画的に口紅を用いることにした。美里と入れ替わったあとに、美里の友達などに怪しまれてしまっては立つ瀬がない。非現実的とはいえ、仮にもこの口紅の存在や正体が露見することはあってはならない。自分が実は美里ではないと、疑われてはいけない。
入れ替わった後にも周りから怪しまれることがないように、理沙子は美里のことを徹底的に研究した。
彼女の身長、体重、誕生日、血液型、好きなアイドル、親の名前…。誰かに尋ねられそうな事象はひとまず頭に叩き込んだ。
彼女が大学に遅刻しそうな時の表情、友達の欠席を心配する悲しげな表情、仲間を責め立てる表情。彼女の振る舞いも研究した。陰気な自分を押し殺し、いわば美里をトレースするのだ。
理沙子は美里の狼狽する姿を想像した。普段から笑みを絶やさない美里が、自分のような逸れ者の立場を手に入れてしまったことを自覚し、焦りに飽和する姿。想像するだけで、理沙子は似合わない優越感が生まれるようで面白い。
——————
さて、実際に理沙子が口紅を使用した後、理沙子は記憶障害のふりをした。無事成功して入れ替わったというのに、そこで美里のふりをすることは一切しなかったのだ。
では、どうせ記憶障害ということにするのに、理沙子はなぜ美里のことを先のように徹底的に研究したのだろうか?
23年06月21日 23:10
【ウミガメのスープ】 [みさこ]
【ウミガメのスープ】 [みさこ]

ご参加ありがとうございました!(๑>◡<๑)
解説を見る
簡易解説
実際に入れ替わる前から美里のふりをすることで理沙子自身が『身体が入れ替わってしまった美里だと思い込むおかしな人』を演じ、口紅を使用したタイミングを曖昧にするため。
(オオカミ少年を想像してもらえると展開がわかりやすい。)
詳述
全てを失った私は、その路頭で起死回生のアイテムをもらった。『路頭に迷う』とはよくいうものだが、それはひとえに悪いことにはないようである。
その口紅は、最近の世間で都市伝説みたいに話題になっている『人と入れ替わることができる口紅』その物だった。実現しているのか激しい議論が起こっていたが、まさか本当に実在していたなんて。
あの商人がなぜ私なんかにこれをくれたのかはわからないが、使うことに迷わなかった。
恋人には無碍に捨てられ、そのためにできた借金も残り、恋人といるために捨てた友達への信用も元に戻らない。あるいはこうした苦悩の果て、ついには記憶障害に陥った。そんな状況。
私の中には、楽しかった頃の記憶はない。今を取り巻く絶望だけが、私の全てだった。
『理沙子』という自分に未練などない。今すぐに、幸せな誰かと成り代わりたかった。
ターゲットは簡単に定められた。後輩の美里。私の記憶の中に残る少ない人物だった。
天衣無縫で活発可憐。それにおしゃれで容姿端麗な美里を嫌うものはいない。女子はもちろん、男子の思いも無意識に独り占めにする子だった。
それは私のかつての恋人も、例外ではなかった。だから私が捨てられたというのは、別にどうでもいいけれど。
陰気で卑屈な自分を捨てるには、美里と入れ替わるしかない。狭い視野のうちそう確信していたが、私には都合の悪いことが一つあった。
この口紅のことが、都市伝説並みでも知れ渡っていることである。
もちろん、多くの人は(現に今までの私だって)そんな非科学的なものを信じていない。私が今すぐに美里にキスしても、疑いの余地は残らないかもしれない。
しかし、多くの人の脳裏に口紅がよぎるのも事実なんだ。
私と美里がいきなり入れ替わったら、美里はひどく狼狽するだろう。そして私の身体で、自分は本当は美里なんだと連呼する。初めはみんな本気にしなくとも、やがて疑い始める人が現れるかもしれない。この口紅を頭に浮かべながら。
その疑いは非現実的かもしれないけど、数多くのうちの誰かは徹底的に調べるだろう。そして、君は本当に美里なのか、と両人に尋ねる。そこで私の姿の美里が次々に自分のプロフィールを言い当てていけば、その疑いは大きくなる。美里のふりをしなければならない私は、それを覆すほどうまく美里のふりができるだろうか?
どこかでボロを出してしまうに違いない。確信こそされなくても、「この子はもしかすると美里ではない」と疑い思われ続けて生きるのは苦痛だ。しかも、そのまま月日が経ってもし口紅の存在が都市伝説の域を出て明らかになれば、その疑いは確信に変わりうる。
それならば始めから美里のふりをしなければいいかとも思うが、諦めてただ単に記憶障害のふりをしても、疑いは生まれるもの。私の姿をした美里が必死に訴える不自然さには変わりがないのだから、むしろこちらが弁明できないことが不利になるかもしれない。
どうすれば入れ替わった後も怪しまれずにいられるか。美里の姿で美里のふりをすることを諦めた私は、ある計画を思いついた。
すなわち、今まさに問題になっている疑われ方を、そのまま利用するのだ。
-入れ替わった後にも周りから怪しまれることがないように、理沙子は美里のことを徹底的に研究した。
彼女の身長、体重、誕生日、血液型、好きなアイドル、親の名前…。誰かに尋ねられそうな事象はひとまず頭に叩き込んだ。
彼女が大学に遅刻しそうな時の表情、友達の欠席を心配する悲しげな表情、仲間を責め立てる表情。彼女の振る舞いも研究した。陰気な自分を押し殺し、いわば美里をトレースするのだ。-
しかし、そのトレースを実行するのは美里の姿でではない。私の姿でである。
「お願いみんな!信じてよ!
私は本当は有坂 美里なの!
誕生日は6/22、B型で、あとは、サークルのみんなの名前も知ってる!それに小学校の頃には…。」
私の姿のまま、『身体が入れ替わって狼狽する美里』を演じる。そうすれば先のように、初めは誰もが冗談としてしか相手にしないが、やがて口紅の都市伝説を挙げる者が現れる。完璧に美里のふりをするのは難しいかもしれないけど、『この人は実は本当に美里なのではないか』と疑わせるくらいなら私にもできそうだ。
そして、誰かが本物の美里に尋ねる。『君は本当に美里なのか?』それを返答するのは他でもない美里なのだから、いくら質問しても質問する人たちの持つ疑いが晴れていくだけ。
「ごめん、やっぱり美里は美里だよね。
あんな都市伝説、あるわけないか。」
「あの女の人がおかしいだけだったんだ。
変な噂で疑っちゃってごめんね、美里ちゃん。」
純粋な美里を疑ったことに、周囲は罪悪感すら持ち始める。そして友達の多い美里はどんどん信頼を獲得し、私『理沙子』はただの『自分が、身体が入れ替わってしまった美里だと思い込むおかしな人』と一蹴され始める。
「どうして…。どうしてみんな信じてくれないの!」
-理沙子は美里の狼狽する姿を想像した。普段から笑みを絶やさない美里が、自分のような逸れ者の立場を手に入れてしまったことを自覚し、焦りに飽和する姿。想像するだけで、理沙子は似合わない優越感が生まれるようで面白い。-
その想像を一つ一つ形にして演じる私。完全に周囲に軽蔑されゆくまで、私は自分の姿のまま、狼狽し焦り絶望する美里を演じ続けた。
そして、そうなってから件の口紅を使った。
夜、授業帰りに遅くなった美里の頭を背後から殴る。この後この身体は記憶障害ということになることもあって、気絶させるには一石二鳥だ。
気絶した美里と無理やりキスをした後は、口紅は捨てた。なるべく口紅の存在が露見しないためだ。
そうして翌日、美里の姿となった私は、大学構内でまた一人の女性が奇妙なことを騒ぎ立てているということを耳にする。
「お願いみんな!信じてよ!
私は本当は有坂 美里なの!
誕生日は6/22、B型で、あとは、サークルのみんなの名前も知ってる!それに小学校の頃には…。」
本物の美里である。しかし、その『理沙子』を信じる者はもう一人もいない。この前までは私が演じていたということを弁明しようが、美里を信じる人はすでにいないのだ。
「どうして…。どうしてみんな信じてくれないの!」
そして私は、自分が『殴られた』傷の悪化によって記憶障害になったことにした。これで何を尋ねられることもないし、周囲は私をただ憐れむだけだろう。診断だって、私は口紅を使う前より元から現に記憶障害なのだから、そう下されるだけ。
いずれ、『私を殴った』犯人も『理沙子』だと特定され、彼女は捕まる。大方、『自分が美里だと思い込むあまり、錯乱して本物の美里を襲ったのだろう』と推測されるのではないか。
私は今、長い間大学で話題になっていた異常者に襲われ、記憶障害になった哀れな被害者なんだ。始め美里を本物の美里か疑った人たちも、前にあらぬ疑いをかけた罪悪感から同じ疑いを生むことはほとんど絶対にない。
やがて私の美里のふりが不完全で齟齬が生じても、記憶障害のせいにできるし、少しずつ記憶が回復するふりをすれば、周囲は私を優しく扱ってくれる。
嘘をつき続けて本当を喰らうオオカミ少年。
私はそれを一人二役で行ったことで、ついに完全に美里と成り替わることができた。
病室に一人、美里は微かに笑みを浮かべた。
実際に入れ替わる前から美里のふりをすることで理沙子自身が『身体が入れ替わってしまった美里だと思い込むおかしな人』を演じ、口紅を使用したタイミングを曖昧にするため。
(オオカミ少年を想像してもらえると展開がわかりやすい。)
詳述
全てを失った私は、その路頭で起死回生のアイテムをもらった。『路頭に迷う』とはよくいうものだが、それはひとえに悪いことにはないようである。
その口紅は、最近の世間で都市伝説みたいに話題になっている『人と入れ替わることができる口紅』その物だった。実現しているのか激しい議論が起こっていたが、まさか本当に実在していたなんて。
あの商人がなぜ私なんかにこれをくれたのかはわからないが、使うことに迷わなかった。
恋人には無碍に捨てられ、そのためにできた借金も残り、恋人といるために捨てた友達への信用も元に戻らない。あるいはこうした苦悩の果て、ついには記憶障害に陥った。そんな状況。
私の中には、楽しかった頃の記憶はない。今を取り巻く絶望だけが、私の全てだった。
『理沙子』という自分に未練などない。今すぐに、幸せな誰かと成り代わりたかった。
ターゲットは簡単に定められた。後輩の美里。私の記憶の中に残る少ない人物だった。
天衣無縫で活発可憐。それにおしゃれで容姿端麗な美里を嫌うものはいない。女子はもちろん、男子の思いも無意識に独り占めにする子だった。
それは私のかつての恋人も、例外ではなかった。だから私が捨てられたというのは、別にどうでもいいけれど。
陰気で卑屈な自分を捨てるには、美里と入れ替わるしかない。狭い視野のうちそう確信していたが、私には都合の悪いことが一つあった。
この口紅のことが、都市伝説並みでも知れ渡っていることである。
もちろん、多くの人は(現に今までの私だって)そんな非科学的なものを信じていない。私が今すぐに美里にキスしても、疑いの余地は残らないかもしれない。
しかし、多くの人の脳裏に口紅がよぎるのも事実なんだ。
私と美里がいきなり入れ替わったら、美里はひどく狼狽するだろう。そして私の身体で、自分は本当は美里なんだと連呼する。初めはみんな本気にしなくとも、やがて疑い始める人が現れるかもしれない。この口紅を頭に浮かべながら。
その疑いは非現実的かもしれないけど、数多くのうちの誰かは徹底的に調べるだろう。そして、君は本当に美里なのか、と両人に尋ねる。そこで私の姿の美里が次々に自分のプロフィールを言い当てていけば、その疑いは大きくなる。美里のふりをしなければならない私は、それを覆すほどうまく美里のふりができるだろうか?
どこかでボロを出してしまうに違いない。確信こそされなくても、「この子はもしかすると美里ではない」と疑い思われ続けて生きるのは苦痛だ。しかも、そのまま月日が経ってもし口紅の存在が都市伝説の域を出て明らかになれば、その疑いは確信に変わりうる。
それならば始めから美里のふりをしなければいいかとも思うが、諦めてただ単に記憶障害のふりをしても、疑いは生まれるもの。私の姿をした美里が必死に訴える不自然さには変わりがないのだから、むしろこちらが弁明できないことが不利になるかもしれない。
どうすれば入れ替わった後も怪しまれずにいられるか。美里の姿で美里のふりをすることを諦めた私は、ある計画を思いついた。
すなわち、今まさに問題になっている疑われ方を、そのまま利用するのだ。
-入れ替わった後にも周りから怪しまれることがないように、理沙子は美里のことを徹底的に研究した。
彼女の身長、体重、誕生日、血液型、好きなアイドル、親の名前…。誰かに尋ねられそうな事象はひとまず頭に叩き込んだ。
彼女が大学に遅刻しそうな時の表情、友達の欠席を心配する悲しげな表情、仲間を責め立てる表情。彼女の振る舞いも研究した。陰気な自分を押し殺し、いわば美里をトレースするのだ。-
しかし、そのトレースを実行するのは美里の姿でではない。私の姿でである。
「お願いみんな!信じてよ!
私は本当は有坂 美里なの!
誕生日は6/22、B型で、あとは、サークルのみんなの名前も知ってる!それに小学校の頃には…。」
私の姿のまま、『身体が入れ替わって狼狽する美里』を演じる。そうすれば先のように、初めは誰もが冗談としてしか相手にしないが、やがて口紅の都市伝説を挙げる者が現れる。完璧に美里のふりをするのは難しいかもしれないけど、『この人は実は本当に美里なのではないか』と疑わせるくらいなら私にもできそうだ。
そして、誰かが本物の美里に尋ねる。『君は本当に美里なのか?』それを返答するのは他でもない美里なのだから、いくら質問しても質問する人たちの持つ疑いが晴れていくだけ。
「ごめん、やっぱり美里は美里だよね。
あんな都市伝説、あるわけないか。」
「あの女の人がおかしいだけだったんだ。
変な噂で疑っちゃってごめんね、美里ちゃん。」
純粋な美里を疑ったことに、周囲は罪悪感すら持ち始める。そして友達の多い美里はどんどん信頼を獲得し、私『理沙子』はただの『自分が、身体が入れ替わってしまった美里だと思い込むおかしな人』と一蹴され始める。
「どうして…。どうしてみんな信じてくれないの!」
-理沙子は美里の狼狽する姿を想像した。普段から笑みを絶やさない美里が、自分のような逸れ者の立場を手に入れてしまったことを自覚し、焦りに飽和する姿。想像するだけで、理沙子は似合わない優越感が生まれるようで面白い。-
その想像を一つ一つ形にして演じる私。完全に周囲に軽蔑されゆくまで、私は自分の姿のまま、狼狽し焦り絶望する美里を演じ続けた。
そして、そうなってから件の口紅を使った。
夜、授業帰りに遅くなった美里の頭を背後から殴る。この後この身体は記憶障害ということになることもあって、気絶させるには一石二鳥だ。
気絶した美里と無理やりキスをした後は、口紅は捨てた。なるべく口紅の存在が露見しないためだ。
そうして翌日、美里の姿となった私は、大学構内でまた一人の女性が奇妙なことを騒ぎ立てているということを耳にする。
「お願いみんな!信じてよ!
私は本当は有坂 美里なの!
誕生日は6/22、B型で、あとは、サークルのみんなの名前も知ってる!それに小学校の頃には…。」
本物の美里である。しかし、その『理沙子』を信じる者はもう一人もいない。この前までは私が演じていたということを弁明しようが、美里を信じる人はすでにいないのだ。
「どうして…。どうしてみんな信じてくれないの!」
そして私は、自分が『殴られた』傷の悪化によって記憶障害になったことにした。これで何を尋ねられることもないし、周囲は私をただ憐れむだけだろう。診断だって、私は口紅を使う前より元から現に記憶障害なのだから、そう下されるだけ。
いずれ、『私を殴った』犯人も『理沙子』だと特定され、彼女は捕まる。大方、『自分が美里だと思い込むあまり、錯乱して本物の美里を襲ったのだろう』と推測されるのではないか。
私は今、長い間大学で話題になっていた異常者に襲われ、記憶障害になった哀れな被害者なんだ。始め美里を本物の美里か疑った人たちも、前にあらぬ疑いをかけた罪悪感から同じ疑いを生むことはほとんど絶対にない。
やがて私の美里のふりが不完全で齟齬が生じても、記憶障害のせいにできるし、少しずつ記憶が回復するふりをすれば、周囲は私を優しく扱ってくれる。
嘘をつき続けて本当を喰らうオオカミ少年。
私はそれを一人二役で行ったことで、ついに完全に美里と成り替わることができた。
病室に一人、美里は微かに笑みを浮かべた。