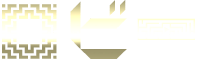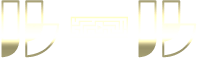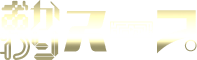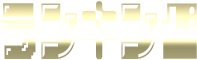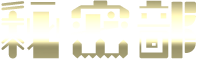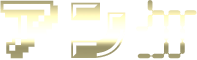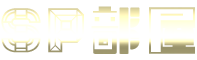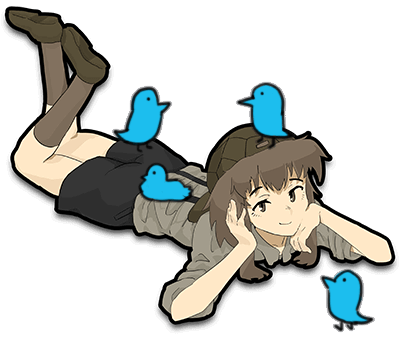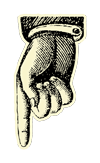「もしも田中が弾けたなら」「6ブックマーク」
田中が「ピアノを弾けるようにしてください」とお願いしたら、ピアノが宙に浮き始めた。
一体なぜ?

一体なぜ?
21年11月26日 13:18
【ウミガメのスープ】 [ダニー]
【ウミガメのスープ】 [ダニー]

今日の0:00に締めます。
解説を見る
ハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノを購入した田中。
田中はハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノの為に自宅の2階に完全防音のピアノルームを用意しており、ハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノの到着を心待ちにしていた。
そして運送業者がハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノを田中の家まで届けにやってきた。
しかしハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノはそこそこ大きく、玄関は通ったものの階段の通路の幅を通り抜けることが出来なかった。
「ううむ、ここからハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノを2階に運ぶのは難しいですね…」と運送業者。
「せっかく2階にハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノを置く用の部屋を作ったんです。なんとかそこでピアノを弾けるようにしてください」とお願いする田中。
「よし!ではクレーンでハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノを吊って、2階のあそこの大きな窓から入れましょう」
運送業者はクレーンを手配し、ハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノを吊り上げた。
宙に浮くハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノ。
それを少年のような瞳で見上げる田中。
突然の突風ではちゃめちゃに揺れるハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノ。
慌てふためく運送業者。
田中家の2階の壁をぶち破って無事部屋に着地したハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノ。
なぜか拍手しちゃう田中。
運送業者は思った。
(100円ショップのカラビナは信頼できない)と。
田中はハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノの為に自宅の2階に完全防音のピアノルームを用意しており、ハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノの到着を心待ちにしていた。
そして運送業者がハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノを田中の家まで届けにやってきた。
しかしハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノはそこそこ大きく、玄関は通ったものの階段の通路の幅を通り抜けることが出来なかった。
「ううむ、ここからハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノを2階に運ぶのは難しいですね…」と運送業者。
「せっかく2階にハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノを置く用の部屋を作ったんです。なんとかそこでピアノを弾けるようにしてください」とお願いする田中。
「よし!ではクレーンでハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノを吊って、2階のあそこの大きな窓から入れましょう」
運送業者はクレーンを手配し、ハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノを吊り上げた。
宙に浮くハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノ。
それを少年のような瞳で見上げる田中。
突然の突風ではちゃめちゃに揺れるハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノ。
慌てふためく運送業者。
田中家の2階の壁をぶち破って無事部屋に着地したハイパーエキゾチックニューロマンスタンダードグランドピアノ。
なぜか拍手しちゃう田中。
運送業者は思った。
(100円ショップのカラビナは信頼できない)と。
「【月刊らてらて〜あなたが選ぶ今月の一杯〜】2021-11月号」「6ブックマーク」
みなさま、こんにちは!
本企画の司会者、マクガフィンでございます。今回もよろしくお願いします!
毎月ご参加いただいている皆様におかれましては、今月でもう2021年が終わるという事実をどのように感じていらっしゃるでしょうか?
個人的にはあっという間の1年でしたので、もうそんな時期なのか…と少々驚いております。毎月この企画をやっているので時の流れは感じるはずなのですが…はて…?
さて、今回が第33弾となります月刊らてらてですが、簡単にシステムをご説明いたします。
①毎月頭に、先月出題の問題の中からブクマ数・いいね数が多かったものをエントリー作品として秘密の部屋に掲示いたします。(選考基準は秘密の部屋にて掲載)
②掲示日から3〜4日の間、エントリー作品以外の作品の中から推薦を募り、複数人から推薦された作品をエントリーに加えます。
③本投票(これ)を出題し、一週間ほどの投票期間を設けます。
④締め切り後こちらで開票を行い、得票数が最も多かった作品にタグ「らてらておぶざまんす!」を付けさせていただきます。
☆投票について
本企画は、毎月のスープの中からこれぞ今月のスープだ!とみなさんが思う作品を決めるものです。もっといろんな人に知ってほしい、自分もこんなスープがつくりたい、試みが画期的、この発想はなかった、など、どんな理由でもかまいません。周囲に紹介したくなるスープに票を入れてください。あくまでみなさんが選ぶ今月の一杯です。深く考えず直感で選んでいただいてかまいません。
☆投票上の注意
・投票は闇スープ状態で行います。
・投票に際し、みなさんは1人2票を持っています。2作品に1票ずつ投じるもよし、1つに2票投じるもよし、1票だけ使用するもよしとします。
・自分の作品、SPをした作品等にも投票していただいてかまいません。
・投票の際に問題への感想を添えていただいてもかまいません。もちろんなくても大丈夫です。
※テンプレートの感想欄に(ネタバレあり/なし)の項目があります。出題者様やこれから作品を楽しみたいユーザー様のためにも、ぜひご活用くださいませ。(感想は自由に書いていただいて構いません。)
☆投票テンプレート
No.(番号)『◯◯◯』(………さん) に1票
No.(番号)『◯◯◯』(………さん) に1票
[感想](ネタバレあり/なし)
・・・・・・・・・・・。
☆月刊らてらてではバッジコインが実装されております。本企画の終了後、司会者がミニメールにて入賞&参加賞を贈呈いたします。賞品は以下の通りです。
1位:300コイン
2位:150コイン
3位:50コイン
参加賞:10コイン
それでは、先月のエントリー作品はこちら!
☆☆☆エントリー作品一覧☆☆☆
①×の-(闇汁さん)
https://late-late.jp/mondai/show/15313
②贋作 ウミガメのスープ(ボージャック夫人さん)
https://late-late.jp/mondai/show/15337
③[ラテシンからの刺客]百害あるが一縷のホープ(おしゃけさんさん)
https://late-late.jp/mondai/show/15345
④取り調べの極意(ベルンカステルさん)
https://late-late.jp/mondai/show/15398
⑤人ならざるものとパーティーを(霜ばしらさん)
https://late-late.jp/mondai/show/15407
⑥誤ー飲ぐマイウェイ(だだだだ3号機さん)
https://late-late.jp/mondai/show/15411
⑦謎解きの間〜雪月花〜(ベルンカステルさん)
https://late-late.jp/mondai/show/15428
⑧感謝還元カンカン照り(ルーシーさん)
https://late-late.jp/mondai/show/15458
⑨夜の激辛カップ麺(ひゅーさん)
https://late-late.jp/mondai/show/15369
⑩もしも田中が弾けたなら(ダニーさん)
https://late-late.jp/mondai/show/15433
今回エントリーされた作品について、タグ『らてらておぶざまんす?2021-11』で一括管理させていただいております。
エントリー作品を見るときは、
問題一覧→タグ一覧→タグ検索→らてらておぶざまんす?→2021-11とついた問題を確認する
という流れが効率的です。
または、この問題文のリンクから直接問題ページにとぶことも可能です。
投票締め切りは『12月19日(日)21:59まで』となります。それまでの期間なら、投票内容の変更も可能です。
最後になりますが、本企画は古参新参問わず多くの方にご参加いただきたいと思っております!
自分はちょっと…と気にすることなく、ドシドシ投票ください!お待ちしております!

本企画の司会者、マクガフィンでございます。今回もよろしくお願いします!
毎月ご参加いただいている皆様におかれましては、今月でもう2021年が終わるという事実をどのように感じていらっしゃるでしょうか?
個人的にはあっという間の1年でしたので、もうそんな時期なのか…と少々驚いております。毎月この企画をやっているので時の流れは感じるはずなのですが…はて…?
さて、今回が第33弾となります月刊らてらてですが、簡単にシステムをご説明いたします。
①毎月頭に、先月出題の問題の中からブクマ数・いいね数が多かったものをエントリー作品として秘密の部屋に掲示いたします。(選考基準は秘密の部屋にて掲載)
②掲示日から3〜4日の間、エントリー作品以外の作品の中から推薦を募り、複数人から推薦された作品をエントリーに加えます。
③本投票(これ)を出題し、一週間ほどの投票期間を設けます。
④締め切り後こちらで開票を行い、得票数が最も多かった作品にタグ「らてらておぶざまんす!」を付けさせていただきます。
☆投票について
本企画は、毎月のスープの中からこれぞ今月のスープだ!とみなさんが思う作品を決めるものです。もっといろんな人に知ってほしい、自分もこんなスープがつくりたい、試みが画期的、この発想はなかった、など、どんな理由でもかまいません。周囲に紹介したくなるスープに票を入れてください。あくまでみなさんが選ぶ今月の一杯です。深く考えず直感で選んでいただいてかまいません。
☆投票上の注意
・投票は闇スープ状態で行います。
・投票に際し、みなさんは1人2票を持っています。2作品に1票ずつ投じるもよし、1つに2票投じるもよし、1票だけ使用するもよしとします。
・自分の作品、SPをした作品等にも投票していただいてかまいません。
・投票の際に問題への感想を添えていただいてもかまいません。もちろんなくても大丈夫です。
※テンプレートの感想欄に(ネタバレあり/なし)の項目があります。出題者様やこれから作品を楽しみたいユーザー様のためにも、ぜひご活用くださいませ。(感想は自由に書いていただいて構いません。)
☆投票テンプレート
No.(番号)『◯◯◯』(………さん) に1票
No.(番号)『◯◯◯』(………さん) に1票
[感想](ネタバレあり/なし)
・・・・・・・・・・・。
☆月刊らてらてではバッジコインが実装されております。本企画の終了後、司会者がミニメールにて入賞&参加賞を贈呈いたします。賞品は以下の通りです。
1位:300コイン
2位:150コイン
3位:50コイン
参加賞:10コイン
それでは、先月のエントリー作品はこちら!
☆☆☆エントリー作品一覧☆☆☆
①×の-(闇汁さん)
https://late-late.jp/mondai/show/15313
②贋作 ウミガメのスープ(ボージャック夫人さん)
https://late-late.jp/mondai/show/15337
③[ラテシンからの刺客]百害あるが一縷のホープ(おしゃけさんさん)
https://late-late.jp/mondai/show/15345
④取り調べの極意(ベルンカステルさん)
https://late-late.jp/mondai/show/15398
⑤人ならざるものとパーティーを(霜ばしらさん)
https://late-late.jp/mondai/show/15407
⑥誤ー飲ぐマイウェイ(だだだだ3号機さん)
https://late-late.jp/mondai/show/15411
⑦謎解きの間〜雪月花〜(ベルンカステルさん)
https://late-late.jp/mondai/show/15428
⑧感謝還元カンカン照り(ルーシーさん)
https://late-late.jp/mondai/show/15458
⑨夜の激辛カップ麺(ひゅーさん)
https://late-late.jp/mondai/show/15369
⑩もしも田中が弾けたなら(ダニーさん)
https://late-late.jp/mondai/show/15433
今回エントリーされた作品について、タグ『らてらておぶざまんす?2021-11』で一括管理させていただいております。
エントリー作品を見るときは、
問題一覧→タグ一覧→タグ検索→らてらておぶざまんす?→2021-11とついた問題を確認する
という流れが効率的です。
または、この問題文のリンクから直接問題ページにとぶことも可能です。
投票締め切りは『12月19日(日)21:59まで』となります。それまでの期間なら、投票内容の変更も可能です。
最後になりますが、本企画は古参新参問わず多くの方にご参加いただきたいと思っております!
自分はちょっと…と気にすることなく、ドシドシ投票ください!お待ちしております!
21年12月10日 00:08
【新・形式】 [「マクガフィン」]
【新・形式】 [「マクガフィン」]

結果発表致しました!総票数42票の大接戦を制した作品とは…!?
解説を見る
たくさんの投票ありがとうございました!
今回は21人の皆様にご参加いただき、総票数は42票となりました!
いつのまにか訪れた圧倒的年末、ほにゃららグランプリとほぼ同じ締切と投票しにくい中だったかとは思いますが、これだけの方にご参加いただけたのもやはり良いスープばかりだったからだと思います。
それでは早速エントリー作品の投票結果を発表していきます!
第3位 7票(10pt) 50コイン獲得
①×の−(闇汁さん)
第2位 7票(15pt) 150コイン獲得
⑤人ならざるものとパーティーを(霜ばしらさん)
そして今回の月刊らてらて2021-11月号、今月のスープは…
第1位 8票(9pt) 300コイン獲得
②贋作 ウミガメのスープ(ボージャック夫人さん)
という結果になりました!
票を獲得した方々、エントリーされた方々、おめでとうございます🎉🎊
(入賞&参加賞は開票後、ミニメールにて司会者から配布いたします。)
見事1位を獲得した『贋作 ウミガメのスープ』には、タグ『らてらておぶざまんす!』をつけさせていただきます(勝手に)。
毎度のことだと言えばその通りなのですが、集計をしていく身としましては今月はいつにも増して大激戦だなというふうに感じておりました。ある問題に票が入ればまた別の問題が並ぶ、その繰り返しで誰も結果が予測できない回になったのではないでしょうか!
最後になりますが、投票にご参加いただき本当にありがとうございました!
来月以降も開催したいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
それでは先月号はこれでおしまい!
今月もみなさん楽しみましょう!
それではご一緒に〜 せぇのっ
Let'sらてらて〜
今回は21人の皆様にご参加いただき、総票数は42票となりました!
いつのまにか訪れた圧倒的年末、ほにゃららグランプリとほぼ同じ締切と投票しにくい中だったかとは思いますが、これだけの方にご参加いただけたのもやはり良いスープばかりだったからだと思います。
それでは早速エントリー作品の投票結果を発表していきます!
第3位 7票(10pt) 50コイン獲得
①×の−(闇汁さん)
第2位 7票(15pt) 150コイン獲得
⑤人ならざるものとパーティーを(霜ばしらさん)
そして今回の月刊らてらて2021-11月号、今月のスープは…
第1位 8票(9pt) 300コイン獲得
②贋作 ウミガメのスープ(ボージャック夫人さん)
という結果になりました!
票を獲得した方々、エントリーされた方々、おめでとうございます🎉🎊
(入賞&参加賞は開票後、ミニメールにて司会者から配布いたします。)
見事1位を獲得した『贋作 ウミガメのスープ』には、タグ『らてらておぶざまんす!』をつけさせていただきます(勝手に)。
毎度のことだと言えばその通りなのですが、集計をしていく身としましては今月はいつにも増して大激戦だなというふうに感じておりました。ある問題に票が入ればまた別の問題が並ぶ、その繰り返しで誰も結果が予測できない回になったのではないでしょうか!
最後になりますが、投票にご参加いただき本当にありがとうございました!
来月以降も開催したいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
それでは先月号はこれでおしまい!
今月もみなさん楽しみましょう!
それではご一緒に〜 せぇのっ
Let'sらてらて〜
「新ラテシン BS ウミガメのスープです」「6ブックマーク」
カメオはカメコとのデートをとても楽しみにしていたのに
カメオが昨晩、ウミガメのスープを飲んだためにカメコとのデートは中止となった。
一体なぜ?
この問題はBS問題なのです
出題から30分経過するかその前に正解が出ますと1時間のBSタイムに入ります。
BSタイム中はネタ質有り、雑談あり、ボケてよしのマナーと良識を守った無礼講のお祭りタイムに入るのです。
BS終了後は速やかに質問を解く作業に戻るのです
カメオが昨晩、ウミガメのスープを飲んだためにカメコとのデートは中止となった。
一体なぜ?
この問題はBS問題なのです
出題から30分経過するかその前に正解が出ますと1時間のBSタイムに入ります。
BSタイム中はネタ質有り、雑談あり、ボケてよしのマナーと良識を守った無礼講のお祭りタイムに入るのです。
BS終了後は速やかに質問を解く作業に戻るのです
21年12月26日 21:00
【ウミガメのスープ】 [天童 魔子]
【ウミガメのスープ】 [天童 魔子]
解説を見る
海が見えるレストランでウェイターをしていたカメオ。
カメオは昨晩、ある男がウミガメのスープを注文したのですが
その男は最初の一口をスプーンですくいその後は一切口を付けることなくすぐにお会計を支払いかえってしまったのです。
折角のウミガメのスープを片したカメオは勿体ないと思ってしまった。
他人が飲んで残したスープならばカメオも飲もうと思わないが
これは一杯すくっただけで出した状態のまま変わりないじゃないか
第一これいくらすると思ってんだ。なかなか味わえるもんじゃないんだぞ
葛藤したカメオはウミガメのスープの魅力に抗えず飲んでしまったのです。
その後、警察が来て先ほどウミガメのスープを飲んだ男が自殺をしたことを知った。
ただ困ったことに男には何の自殺をする理由も見当たらず
分かっていることはどうやら『ウミガメのスープを飲んだから死んだ』っと言うことだった。
カメオは恐怖した。
怖くて怖くてたまらなかった。
自殺をした人間が飲んだスープ。
自殺の原因となってしまったうみがめのスープ。
カメオには何故男が自殺してしまったのか分からない。
でも解き明かさないと、真相を解明しないと・・・・
だってカメオも食べてしまったのだから!!!!
デートをしている余裕なんてカメオには無かったのです。
呼び止められただけの店員の卑業
皆様ご参加ありがとうございました(゚д゚)ゞ
今年も1年お疲れ様でした。来年もよろしくなのです。
カメオは昨晩、ある男がウミガメのスープを注文したのですが
その男は最初の一口をスプーンですくいその後は一切口を付けることなくすぐにお会計を支払いかえってしまったのです。
折角のウミガメのスープを片したカメオは勿体ないと思ってしまった。
他人が飲んで残したスープならばカメオも飲もうと思わないが
これは一杯すくっただけで出した状態のまま変わりないじゃないか
第一これいくらすると思ってんだ。なかなか味わえるもんじゃないんだぞ
葛藤したカメオはウミガメのスープの魅力に抗えず飲んでしまったのです。
その後、警察が来て先ほどウミガメのスープを飲んだ男が自殺をしたことを知った。
ただ困ったことに男には何の自殺をする理由も見当たらず
分かっていることはどうやら『ウミガメのスープを飲んだから死んだ』っと言うことだった。
カメオは恐怖した。
怖くて怖くてたまらなかった。
自殺をした人間が飲んだスープ。
自殺の原因となってしまったうみがめのスープ。
カメオには何故男が自殺してしまったのか分からない。
でも解き明かさないと、真相を解明しないと・・・・
だってカメオも食べてしまったのだから!!!!
デートをしている余裕なんてカメオには無かったのです。
呼び止められただけの店員の卑業
皆様ご参加ありがとうございました(゚д゚)ゞ
今年も1年お疲れ様でした。来年もよろしくなのです。
「アイドル・アイドラー・アイドリスト」「6ブックマーク」
会社から帰るところだったカメオがめずらしく渋滞に巻き込まれたのは、ド田舎である水平町のご当地アイドルのラテコが想像以上に有名だったからだという。
その日はラテコのライブがあったわけでもないのに一体なぜ?

その日はラテコのライブがあったわけでもないのに一体なぜ?
21年12月26日 22:59
【ウミガメのスープ】 [ほずみ]
【ウミガメのスープ】 [ほずみ]

オフ会で出題した問題です~!スペシャルサンクス:オフ会に参加したみなさん!
解説を見る
A.渋滞のことを知ろうとTwitterで検索してもラテコのことばかりヒットするから
いつも帰るときに使う道路が火事により通行止めになったことを知ったカメオ。
ド田舎なので普通に検索しても情報は得られないので、こういうときはいつもTwitterで情報収集して迂回することにしている。
しかし今日は火事や渋滞の様子を知ろうとTwitterで「水平町」で検索するも、出てくるのは昨日のラテコのライブ『ラテライブ!in水平町ホール』の感想や「水平町で火事?ラテコちゃん大丈夫かなぁ」という書き込みばかり。
ラテコが有名でなければ火事や渋滞の情報を得られて迂回できたのに…と思うカメオであった。
オフ会に参加したのはもとより、今年はTwitterなどでもらてらての方とたくさん交流できて楽しかったのでこれを「わたしにとっての2021年」問題にします!
いつも帰るときに使う道路が火事により通行止めになったことを知ったカメオ。
ド田舎なので普通に検索しても情報は得られないので、こういうときはいつもTwitterで情報収集して迂回することにしている。
しかし今日は火事や渋滞の様子を知ろうとTwitterで「水平町」で検索するも、出てくるのは昨日のラテコのライブ『ラテライブ!in水平町ホール』の感想や「水平町で火事?ラテコちゃん大丈夫かなぁ」という書き込みばかり。
ラテコが有名でなければ火事や渋滞の情報を得られて迂回できたのに…と思うカメオであった。
オフ会に参加したのはもとより、今年はTwitterなどでもらてらての方とたくさん交流できて楽しかったのでこれを「わたしにとっての2021年」問題にします!
「シャイロックのナイフ」「6ブックマーク」
ある日、カメオが殺害された。
凶器はナイフで死因は失血死である。
死体の側にはおびただしい量の血が流れていた。
だが警察の捜査によると、この血はカメオの妻、カメコのものであることが判明し、カメオの血は一滴も検出されなかった。
状況を補完してください。
凶器はナイフで死因は失血死である。
死体の側にはおびただしい量の血が流れていた。
だが警察の捜査によると、この血はカメオの妻、カメコのものであることが判明し、カメオの血は一滴も検出されなかった。
状況を補完してください。
22年01月15日 21:01
【ウミガメのスープ】 [koto]
【ウミガメのスープ】 [koto]
解説を見る
事故に遭ったカメオは病院に運ばれた。
大量に出血しており、すぐにも輸血が必要であったが、あいにくカメオに必要な血液のストックがなかった。
幸いカメオの妻、カメコの血液が適合することがわかり、すぐに採血された。
そしてカメオに輸血を行おうとしたその時だった。
突然、男が現れて輸血パックをナイフで刺し貫いたのだ。
男は病院の関係者で、常日頃からカメオに強い恨みを抱いていたという。
ナイフで空いた穴から採血したばかりのカメコの血が辺り一面にぶち巻かれる。
こうして、輸血が間に合わず、カメオは失血死をしてしまったのだった。
大量に出血しており、すぐにも輸血が必要であったが、あいにくカメオに必要な血液のストックがなかった。
幸いカメオの妻、カメコの血液が適合することがわかり、すぐに採血された。
そしてカメオに輸血を行おうとしたその時だった。
突然、男が現れて輸血パックをナイフで刺し貫いたのだ。
男は病院の関係者で、常日頃からカメオに強い恨みを抱いていたという。
ナイフで空いた穴から採血したばかりのカメコの血が辺り一面にぶち巻かれる。
こうして、輸血が間に合わず、カメオは失血死をしてしまったのだった。